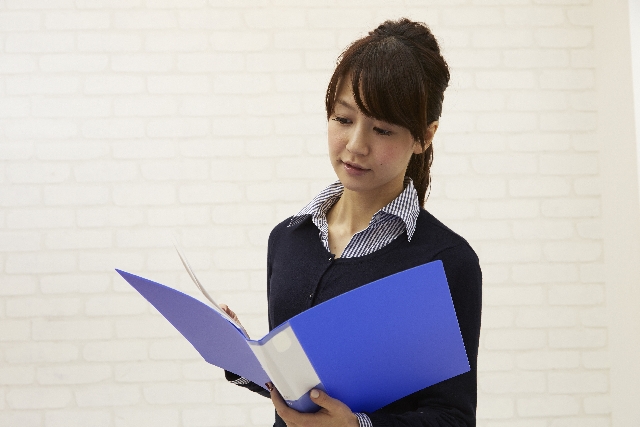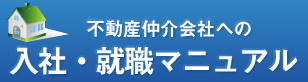住宅ローン、借金、支払い、厳しい
住宅ローンの支払いが厳しい場合の対策についてまとめました。相談する相手を順番にしましたので、参考にしてください。
1.フィナンシャルプランナー
まずは、生活を見直しましょう。
①収入を増やす
・副業
・配偶者のバイト
②支出を減らす
2.銀行
住宅ローンの支払を一時的に猶予してもらうリスケジュールができないか確認しましょう。
3.弁護士、司法書士
増えてしまった借金を圧縮する方法があります。自宅を手放す必要があり、借金が免責となる破産のほかに、住宅ローン以外の借金を5分の1にし住宅ローンはそのまま支払っていける民事再生という方法があります。
4.不動産会社
やむを得ず自宅の売却が避けられない場合は、なるべく住宅ローンが残らないように高く売りましょう。それも難しい場合は、売却金額が多少低くなってしまったとしても、なるべく自分の手元にお金が残るような売却方法を相談しましょう。
【事前策】
自宅を手放さなければならないが、自宅の売却価格より住宅ローンの残りが多くて売却もできない。そんな事態を防ぐためには下記事項に注意しましょう。
・新築を買わない:新築は買って直ぐに500万円くらい値下がりします。
・頭金を入れる:購入時に頭金を1割くらい入れているともし売却となっても残債割れにならずに済みます。
・低い金利で借りる:高い金利で住宅を購入すると無理が生じます。
設備表の注意事項
設備表は、売却不動産に付属する設備の状況について、売主から買主へ説明する書類です。特に不具合のある個所を伝えきれていないと決済後にトラブルになってしまいます。売主は、どんな些細なことでも買主に伝えるようにしましょう。買主は、購入後に不具合が発生することを予期しておく必要があります。
【特に気を付けたい事項】
給湯器:寿命は10年程度です。購入後何年ぐらい経過しているか、お湯の出が不安定になることはないか。
エアコン:善意で置いていったエアコンが故障してトラブルに、というのも珍しくない話です。古いエアコンは売主負担で撤去が原則です。
インターホン:電気系統は一番不具合が出やすく、原因不明であることも多いです。引渡後すぐにインターホンが壊れてトラブルということも多いです。
照明:現在はシーリングに取り付ける照明が主流ですが、昔や特殊な照明などは直付けとなっており、照明撤去後に配線がむき出しになってしまい、新たに照明を取り付けるのに電気工事が必要となる場合があります。
水漏れ:給排水設備で一番トラブルになりやすいのが、水漏れです。特に消耗品であるパッキンからの水漏れは免責になりますが、パッキンのみの交換ができず設備の交換が必要となる場合が多いので注意が必要です。
不動産売却費用
所有不動産を売却する際の費用についてまとめました。
1.契約印紙:売買契約書に貼付する印紙代がかかります。
1,000万円未満→5,000円、5,000万円未満→10,000円、5,000万円以上→30,000円
2.仲介手数料:〈売買代金×3%+60,000円)×消費税※3,000万円→1,036,800円、5,000万円→1,684,800円
3.抵当権抹消費用:抵当権1本につき20,000円前後
4.譲渡税:購入金額より売却代金が多い場合、短期譲渡所得→譲渡益に対し39%、長期譲渡所得→譲渡益に対し20%。
※居住用財産の場合、3,000万円までの軽減措置有。
5.測量費用:土地を売る場合には隣地との境界を明示する必要があります。境界標が入っていない場合、測量が何十年も前の場合、道路査定が終わっていない場合、測量や境界標の復元が必要となってまいります。
新築戸建と中古戸建のメリット・デメリット
新築戸建と中古戸建のメリット・デメリットについてまとめました。
【新築戸建のメリット】
・まだ誰も住んだことがない部屋に最初のオーナーとして住める、贅沢な気分が味わえます。
・10年くらい住んでも販売時にはまだまだ新しい物件と買主に思ってもらえます。
・10年くらいは何の手も入れずに住むことができます。
・どこのハウスメーカーが建てたかで物件の良し悪しの想像ができる。
・建つ前でも別の現場で似たような仕様の家やモデルルームがあるので、完成後の雰囲気の想像がある程度可能。
・新築保証がある為、ある程度の年数までは安心。
【新築戸建のデメリット】
・新築なのに仲介手数料がかかる場合が多いです。
・10年過ぎてから設備や外壁、内装に手を入れる必要が出て来ます。
・土地の相場価格と建物の建築費用を足した金額と新築戸建の購入価格との間に大きな差があります。※新築プレミアム
・人気の物件ともなると完成前に完売となってしまうこともあり、実際に住む家を見てから購入できない場合もある。
・近隣にどのような人が住むことになるのか入居までわからない
【中古戸建のメリット】
・築年数と共に建物価値が下がってくるので相場価格相当の戸建てを買うことができる。
・相場価格が形成されている為、適正な価格で購入することができる。
・購入前に、近隣にどのような人が住んでいるのかわかる
【中古戸建のデメリット】
・見えないところで建物が劣化している。
・不具合が表面化した時は多額の費用がかかる場合がある。
・新築戸建と異なり保証が受けられない。
・経過年数に伴う性能低下や摩耗・損耗については甘受しなければならない。
新築マンションと中古マンションのメリット・デメリット
新築マンションと中古マンションのメリット・デメリットについてまとめました。
【新築マンションのメリット】
・まだ誰も住んだことがない部屋に最初のオーナーとして住める、贅沢な気分が味わえます。
・仲介手数料がかかりませんが、修繕積立基金の支払いがあります。※まれに仲介手数料がかかるマンションもあります。
・最新の設備や仕様を享受できます。マンションは日進月歩で設備や仕様が進化します。
【新築マンションのデメリット】
・購入価格には、新築特有のプレミアム価格がONされている為、中古として売る場合は、マンションによって異なりますが、500万円程度値下がりする場合もあります。
・購入前に実際の部屋を見ることができない。※竣工後未入居物件を除く
・施工の良し悪しが入居するまでわからない。
・隣接住戸にどのような人が住んでいるのか入居までわからない
【中古マンションのメリット】
・新築マンションより割安なマンションがほとんどです。
・売主がこれまでに払ってくれた修繕積立金の利益を享受することができます。
・相場価格が形成されている為、適正な価格で購入することができる。
・購入前に検討している物件を実際に見てみることができる。
・購入前に、隣接住戸にどのような人が住んでいるのかわかる
【中古マンションのデメリット】
・築年数にもよるが、新築の保証が切れている場合があり、補修や交換の費用がかかる場合がある。
・経過年数に伴う性能低下や摩耗・損耗については甘受しなければならない。
・設備や仕様が古い。
不動産売却の流れ~12ステップ~
不動産を売却するときの流れをまとめました。~12ステップ~
1.現在の残債を確認する。
所有不動産売却の大前提となる、ローンの残債を確認しましょう。これによって買い替えができるのか、売却時に持ち出しをしなければならないのか、いくらで売却しなければいけないかの条件がわかります。
2.査定を受ける
実際に不動産仲介会社に所有不動産を内見してもらわなければ、正確な査定金額はわかりません。信頼できる不動産会社2~3社に内見してもらいましょう。多すぎても結果はあまり変わらずにかえって疲れてしまいます。基本的に不動産査定は、(財)不動産流通近代化センターが作成している「価格査定マニュアル」に基づいて行われるので、どこの会社でも出てくる査定結果に大差はありません。
※机上査定は、不動産会社の担当する営業マンによって、依頼を受けたいために高すぎる金額を出したり、依頼を受けてすぐ売れるように低すぎる金額を出してくることもあるので注意が必要です。
3.媒介契約
査定をしてもらったら自分に一番交渉が上手そうな担当者を選びましょう。不動産売却の成否は担当者によって決まると言っても過言ではありません。二人で査定に来る場合は、役職者ではない営業担当がメインになる可能性が高いです。また、試しに仲介手数料の値引きができるか交渉してみましょう。さしたる交渉もなく仲介手数料の値引きに応じてくれるような営業担当は、買主からの交渉にも弱腰で対応する可能性が高いです。
・専属専任媒介契約:不動産仲介会社1社に販売活動を依頼し、売主が自ら見つけた買主と売買する際も必ず不動産仲介会社を媒介する必要がある。
・専任媒介契約:不動産仲介会社1社に販売活動を依頼するも、売主が自ら見つけた買主と売買する場合には、不動産仲介会社を介しなくても良い(その結果仲介手数料を支払う必要がなくなる)。
・一般媒介契約:複数の不動産仲介会社に販売活動を依頼する。売却となった場合には、買主を見つけてくれた不動産仲介会社1社に仲介手数料を支払うことになる。
4.販売活動
媒介契約を締結した後は迅速に販売活動してもらいましょう。買い主は近場にいる可能性が高いです。最寄り駅圏内、同一学区内、同環境内、マンションであれば同じマンション内の買い替え(広い部屋から狭い部屋へ、狭い部屋から広い部屋へ)、マンションに住んでいる方の身内の人が買ったりすることもあります。
・インターネット掲載
最近はインターネットの普及により、新聞折り込み広告を見てお問合わせをするお客様よりもインターネットを見てお問合わせする お客様の方が多いです。新聞をとっていない家庭も増えています。また、近所に販売活動の事実をあまり知られたくない場合でも、インターネットは興味がある人しか見ないため、新聞広告やポスティングチラシが入らなければ販売活動していることを知られることも少ないです。
・新聞折り込み広告やポスティング広告
ご高齢でインターネットを扱えない方や積極的に不動産購入を検討していない方などへの物件告知で有効なのは新聞折り込み広告やポスティングチラシです。特に低金利である昨今は、家賃よりも住宅ローンの方が安い場合が多いため、広告チラシには購入時の毎月の返済礼を記載してもらうようにしましょう。
5.条件交渉
・金額交渉:一番大事なのが金額交渉です。担当営業から交渉を持ちかけられても簡単に応じないようにしましょう。かといって全く値下げをしないというスタンスでは営業マンが最初からあきらめてしまう場合もあります。細心の注意が必要です。自分が譲歩しても良いと思っている金額にするまでに2~3回の交渉を間に挟むようにしましょう。
・引渡期日:特に買い替えの場合で売却先行の場合は、引き渡し期日を6ヵ月程度とってもらうようにしましょう。ある程度厳しめに行っておけばその後の交渉が楽になります。
・手付金:固い契約にするためにはある程度の手付金要求した方が良いでしょう。また、手付解約の場合にはローン解約の時と違って仲介手数料を支払う必要が生じます。営業マンに緩い交渉をされないためにも、営業マンには最初から最低売価の6%以上の手付金が必要になるとプレッシャーを与えておきましょう。
6.契約
・重要事項説明書:主に買主側に対する重要事項説明です。売主としては説明を受けても仕方のない部分ですので、買主への重要事項説明部分には出席しなくても良いケースもあります。
・契約書:売主として注意しておくのは、物件に不具合のあった際には主要な設備で1週間、雨漏り・シロアリ・給排水管・木部の腐食の瑕疵については3か月間の瑕疵担保責任が売主に生じるということです。
・設備表:設備に不具合がある場合にはどんな些細なことでも記入するようにしましょう。特にトラブルが多いのは水漏れです。普段使っていて気にならないものでも買主からすると言っておいて欲しかったというケースが多いです。また、エアコン、照明器具、カーテンの撤去の要否はきちんと確認しましょう。エアコンなどは善意で置いていったにもかかわらず不具合が起きて修理の必要が生じることぐらいつまらないことはありません。基本的には不要な物品・家具等は売主の責任で撤去することになりますので、不要なトラブルを避けたい場合などは最初から撤去するように取り決めておきましょう。
・物件状況等報告書:雨漏り・シロアリ・給排水管の故障・木部の腐食など、瑕疵担保責任を負う箇所についてはどんな些細なことでも申告するようにしましょう。契約前に屋根裏や床下を点検してもらうことが肝要です。
・手付金の受領:買主から受領する手付金は結構な金額になります。手元に置いておくと自然と使ってしまう場合が多いため、必ず支払う必要がある仲介手数料は先に全金払ってしまい、余った金額は繰り上げ返済に充てるようにしましょう。
・契約印紙の貼付:契約書に貼付する印紙代は受領する手付金から支払いができるように不動産仲介会社へ伝えておきましょう。オーバーローンの持ち出しがある場合を除き、売主は基本的には買主からもらう金員から必要経費を支払うことができるので、現金を用意せずに全ての手続きを完了させることができます。
・仲介手数料の支払い:買主からもらった手付金から仲介手数料を支払います。契約時に半金・決済時に半金、契約時若しくは決済時に全金とすることもできます。
7.ローン承認
契約後には1か月程度のローン承認期間が設けられています。契約前の事前承認は得ているため、原則的にはローン不承認となることはないのですが、例えば担保評価が思ったより低くなってしまった・会社の経営悪化等の理由によりローン本申込みの承認が得られない場合もあります。売主としては、ローンが確実になってから繰り上げ返済等の各種手続きを行いましょう。
8.繰り上げ返済
住宅ローンが残っている場合には、対象不動産についている抵当権を所有権移転と同時に抹消する為、抵当権抹消のおよそ10日前~2週間前までに、ローン会社の窓口(平日)に行ってに繰り上げ返済の手続きをしなければなりません。その際、決済時の手続きを司法書士(所有権移転登記費用を負担する買主側が選定します)に委任すること、抹消書類を決済場所近くの支店に移送することをお願いし、なるべく手続きの手間を少なくするようにしましょう。
・火災保険
期間満了以降のの保険金の還付を受けられるように手続きをしておきます。
・ローン保証料
ローン保証料を対象不動産購入時にローン期間満了までの分を現金にて全額支払いしている場合、繰り上げ返済の手続きをすると、全額とまでにはいきませんが、繰り上げ返済以降の分で日割したローン保証料の一部の返還を受けることができます。
9.公的書類の準備
所有権移転の際には売主は権利を失う側のため印鑑証明書が必要となります。また、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所変更登記が必要となる為住民票が必要となります。引越してしまう前に印鑑証明書を取得しておきましょう。印鑑証明書は発行日から3か月間有効です。
10.引越し
引渡猶予がない限り決済前には物件を空にしておかなくてはいけません。引越業者の繁忙期には早い予約が必要となりますので注意が必要です。
11.決済・引き渡し
・残代金の受領
売買代金から手付金を除いた額を買主から受領します。通常は振り込みで売主のローン用口座に全額振り込みますが、ローン残高より残代金が超過する場合には、売主が振込手数料を負担することで複数の口座に分けて超過分を振り込んでもらうようにすることができます。
・抹消費用
住宅ローンが残っており受領する残代金による支払いで完済となる場合、所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記が必要となり、抹消登記を司法書士に依頼するための抹消費用が必要となります。抹消費用は抵当権1本につき20,000円前後になります。
・清算金の受領
固定資産税は1月1日の所有者が納税義務を負うため、売主が支払う必要がありますが引渡日以降の分は日割り計算した額を買主から受領します。また、管理費等についても引渡日以降の分で売主の口座から自動引き落としされてしまう月の分を含めて買主から受領します。
・鍵を渡す
全ての支払が完了した後は買主に鍵を渡します。通常買主の振り込みが売主の口座に着金したことを確認できるようになるまではタイムラグがある為、買主から振込伝票の控えをもらうことで着金確認の代わりとする場合が多いです。早く着金が確認できるようにするために、「至急扱い」であることを銀行窓口で伝えてもらうようにしましょう。
・区分所有者変更届
マンションの場合、お部屋の所有者が変わったことを届け出る必要があります。不動産仲介会社が用意してくるのが通常ですが、管理規約にも届用紙が付いています。
12.不動産譲渡税
売却した不動産の購入価格が、売却価格より低い場合(高い場合でも減価償却により利益がでる場合があります)、その不動産を譲渡したことにより生じた利益について譲渡税(所得税の一種)がかかる場合があります。居住していた財産の売却であれば3,000万円の特別控除が使えますが、空家になっていた等の理由で居住していなかった場合に注意が必要です。
重要事項説明書の流れ
重要事項説明書の流れについてまとめました。契約前に説明される重要事項は主に下記16項目となります。要点を押さえた説明でなければ一般の人にはわかりづらいものです。
1.契約の形態について
売主(私人・法人)と買主(私人・法人)の個人間の取引について、不動産業者間が媒介する形で契約が成立しています。
2.不動産業者の責任の担保について
宅建業保証協会の会員として責任が担保されているのか、企業として法務局に供託金を供与して責任を担保しているのか。
3.不動産の表示について
取引の対象となる不動産を特定するための情報の説明です。法務局に登録されている番号にて不動産を特定します。
4.登記記録事項について
対象不動産に設定されている権利関係の説明です。法務局に登録されている内容です。
5.都市計画法について
建物建築時に都市計画法上制限されている事項の説明です。主に市街化区域(宅地か農地か)や都市計画道路〈建築面積の減少があるか〉についての説明です。
6.建築基準法について
建物建築時に建築基準法上制限されている事項の説明です。建築可能建物の種類を決める用途地域、建築可能な敷地の広さを制限する建ぺい率、建築可能な床面積の広さ(1階と上階の床面積の合計)を制限する容積率、建物の高さの制限、建物を建築できる道路かどうかの建築基準法上の道路種別、接道の長さ等、特に戸建を建築する場合に重要な要素となる事項です。これらの制限によって希望通りの戸建てが建築できない場合もあります。マンションについては、既に建っているので再建築する場合にマンションデベロッパーが対応してくれます。
7.その他の法律の制限について
都市計画法、建築基準法以外の法律による制限の説明です。主に、都市緑地法、景観法、宅地造成等規制法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、文化財保護法、特定都市河川浸水被害対策法などの法律による建築物の制限があります。
8.私道について
接している道路が私道の場合、共有者や権利関係について説明します。基本的に、私道の埋設管(水道管や排水管)は私道所有者が共同で管理することになります。
9.飲用水・電気・ガス・排水について
インフラの整備状況について説明します。特に水道管が細くないか、下水と雨水の処理はどうなっているか(合流か分流か、第三者の配管を使用しているか、第三者の配管が敷設されていないか)が問題となります。
10.管理について
マンションの場合は管理規約や共用部分、負担金、管理状況について説明します。
11.その他の災害区域、アスベスト、耐震診断の状況について説明します。
12.建築時の概要について
建築主や施工会社、設計会社、検査済証はあるのかについて説明します。
13.取引条件について
契約書の重要な事項を抜粋して説明します。
14.保全措置について
取引の履行を保全するために保険を掛けたり供託金を供与するのかについて説明します。
15.ローンについて
契約前に事前承認を得ている住宅ローンの説明をします。
16.その他重要事項について
上記定型事項には該当しないが買主に説明しておくべき重要な事項について説明します。
2015年4月の住宅ローン事情
2015年4月現在の住宅ローンの融資条件についてまとめました。店頭金利、優遇金利、年収400万円以上の返済比率や試算金利、特色など。
①三井住友銀行:店頭金利2.475%、金利優遇1.7%、本体+諸費用+リフォームの可(借入・1.7%優遇、抵当権は1本でOK)。
土日も対応可能。返済比率40%、試算金利4%。派遣社員は不可。勤続3年以上の契約社員は可。建ぺい率・容積率オーバーは20%まで可。
②三菱東京UFJ銀行:店頭金利2.475%、金利優遇1.7%、本体+諸費用+リフォーム可(借入・1.7%優遇、抵当権は要2本)。
平日のみの対応。3年勤続していれば派遣社員や契約社員も可。外国人や外資系、歩合制の営業マンに強い。返済比率35%、試算金利3.55%。
③みずほ銀行:店頭金利2.475%、金利優遇1.7%、本体+諸費用〈金利は1.2%優遇〉OR本体+リフォーム〈金利は1.7%優遇〉。
平日のみの対応。返済比率40%、試算金利4%。ダブルローンが半年間可能。派遣社員は不可。勤続3年以上の契約社員は平均年収の8掛けで返済比率を計算。建ぺい率・容積率オーバーは不可。
④りそな銀行:店頭金利2.475%、金利優遇1.75%、本体+諸費用〈金利は1.7%優遇)OR本体+リフォーム〈金利は1.75%優遇〉。
第2・第4土曜日の対応可能。返済比率35~40%、試算金利3.4%。
年勤続していれば派遣社員や契約社員も可。建ぺい率。容積率オーバーは10%まで。個人信用情報に強い。
⑤三井住友信託銀行:店頭金利2.475%、金利優遇1.75%、公務員・自己資金2割等の高属性が必要。
⑥住信SBIネット銀行:店頭金利2.775%、金利優遇2.175%。事務取扱手数料(保証料)は融資金の2%。
⑦新生銀行:店頭金利1.6%、金利優遇0.72%(半年経過後は金利優遇0.4%)。事務取扱手数料(保証料)は54,000円。
⑧ソニー銀行:店頭金利1.889%、金利優遇1.3%。事務取扱手数料(保証料)は融資金の2.16%
⑨スルガ銀行・ゆうちょ銀行:高齢者の住み替え案件に強い。74歳無職の方でも81歳までの完済、現自宅の売却益を繰り上げ返済することを条件に住み替え先のマンション購入が可能。金利2.475%。
※アパートローンは住宅ローンと取り扱うセクションが異なり、外部に鑑定を依頼する為、事前審査に1か月程度かかる。営業マンは介在せず直接銀行担当者とお客様がやり取りをし、書類については郵送等のやり取りが可能。
不動産仲介手数料を無料にする方法。メリットデメリット。
不動産売買をするときに不動産仲介会社に支払う仲介手数料。
売買価格によってその金額も異なってくることから、売買価格が5,000万円の場合仲介手数料は、1,684,800円にもなる。
これに対し、インターネット等で探すと仲介手数料を半額にしてくれるところや場合によっては無料にしてくれるところもある。
これはどのような仕組みでできているのか。 特に新築戸建てやリノヴェーションマンション等のいわゆる業物(不動産物件の所有者が宅建業者)の場合、不動産仲介会社は売主と買主の両方から仲介手数料をもらうことができる。宅建業者は自分で販売部門をもって転売をしていくよりも無数にある不動産仲介会社に物件の販売活動をしてもらった方がコストが安く済む。
このため販売活動費の代わりとなる仲介手数料を不動産仲介会社に支払っている。仲介手数料の値引きを謳っている不動産仲介会社は、宅建業者から仲介手数料をもらうことで、一般の人から仲介手数料をもらわないような仕組みでやっている。 仲介手数料がかからないのは、当然買主にとってコストが抑えられ、メリットがあることなのだが、当然デメリットもある。
仲介手数料の割引を目当てでくるお客様は、一般のお客様と異なり浮気(他の不動産会社に依頼)することがない。その為、顧客フォローも当然雑になりますし(放っておいてもついてくる)、実際の取引に際しては相手方の不動産会社におんぶにだっことなり、知識不足の営業マンも多い。
なにより一番のデメリットとなるのは値引き交渉だ。宅建業者の販売している不動産は、元々大手不動産仲介会社から物件を仕入れして販売しているケースが圧倒的に多く、これまでの取引や今後の取引もあり営業同士の付き合いも多い。その為、大手不動産仲介会社の営業担当からの値段交渉には応じてくれることが多いが、仲介手数料の割引をしているような会社からの値引きには応じてくれる場合が少ないか応じてくれてもその金額は小さくなりがちだ。
大手不動産仲介会社に値引き交渉してもらった金額(例えば200万円)と不動産仲介手数料を値引きしてもらった金額(30万円)を比べるとその差は歴然としているでしょう。